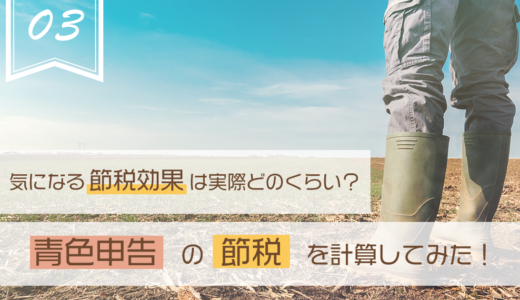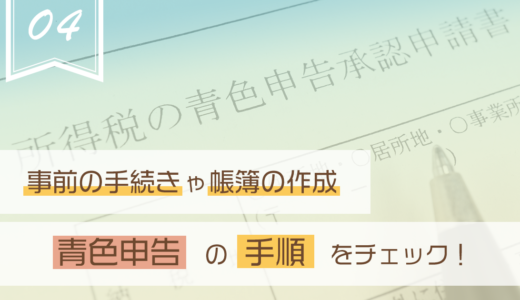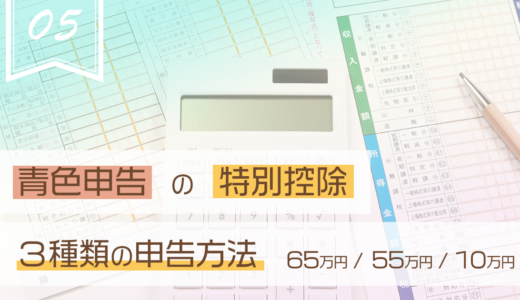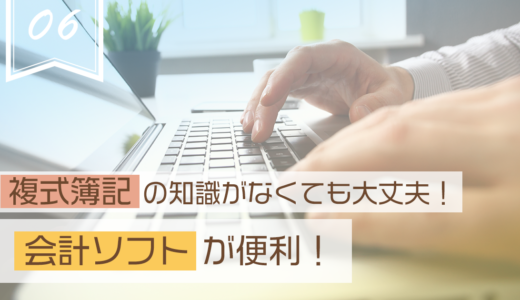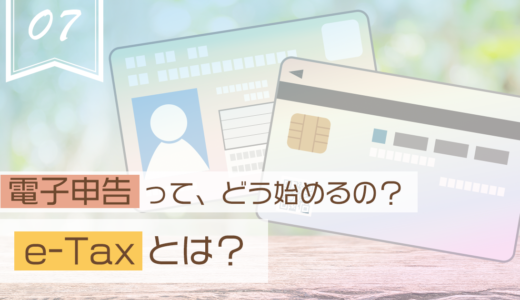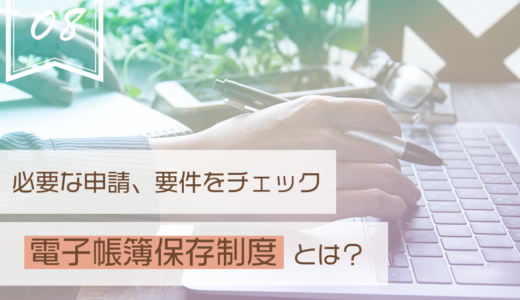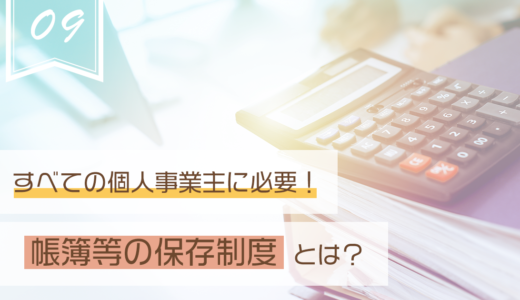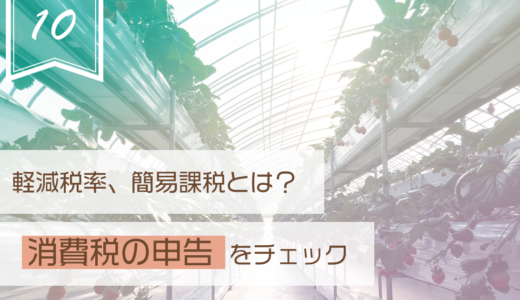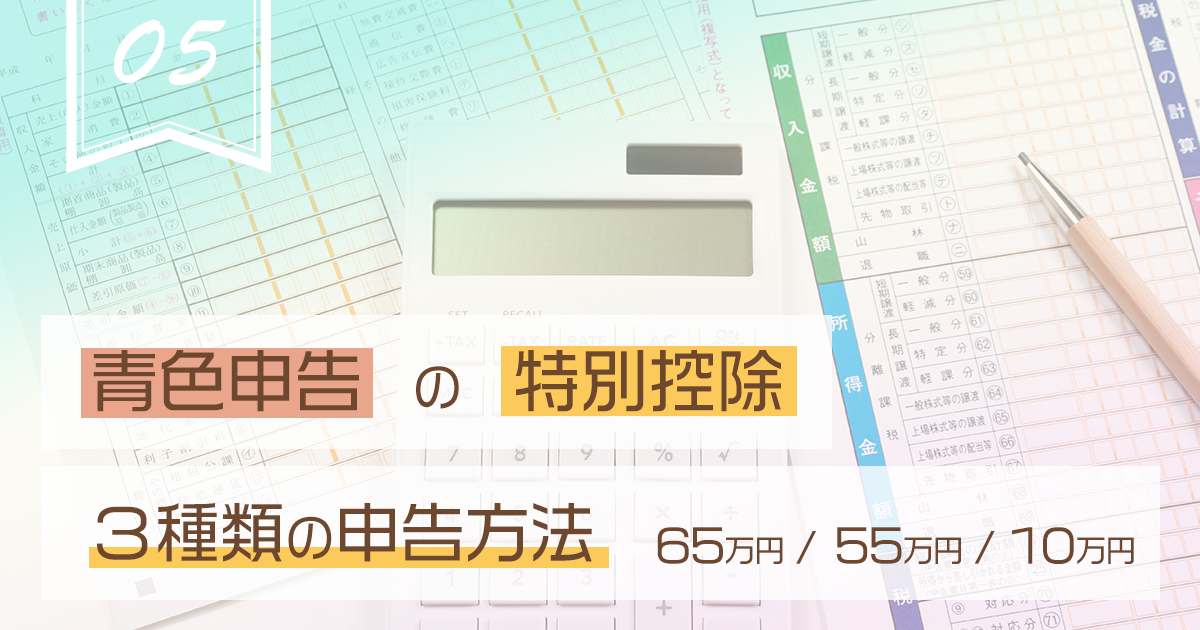
青色申告によって受けられる特別控除は65万円、55万円、10万円の3通りです。
受けるための要件は、控除金額によってそれぞれ異なります。
- 最大65万円控除を受ける場合
- 最大55万円控除を受ける場合
- 最大10万円控除を受ける場合
1.最大65万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳
- 損益計算書の作成
- 貸借対照表の作成
- e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存
取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に必要な書類を添付して提出します。
更に、電子申告(または電子帳簿保存)を行うことで、最大65万円の特別控除を受けることができます。
令和2年度より、所得控除の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられたため、結果としては従来の65万円控除よりも控除額が10万円上乗せとなります。
2.最大55万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳
- 損益計算書の作成
- 貸借対照表の作成
必要な書類については65万円控除と同様ですが、電子申告(または電子帳簿保存)をせずに紙で提出した場合などは、最大55万円控除を受けることができます。
令和2年度より、所得控除の基礎控除が38万円から48万円に引き上げられたため、結果としては従来の65万円控除と同等の控除額となります。
3.最大10万円控除を受ける場合
- 正規の簿記による記帳または、簡易簿記による記帳、現金主義による記帳
- 損益計算書の作成
65万円控除、55万円控除を受けない場合や、簡易簿記による記帳、現金主義による記帳を選択した場合は、基礎控除に加えて最大10万円の特別控除を受けることができます。
また、確定申告書を提出期限内に提出できなかった場合なども、最大10万円の特別控除となります。
まとめ
損益計算書を作成することはいずれも必要ですが、記帳の方法と貸借対照表を作成できるかどうかが大きな分かれ道となります。
自力で作成できればもちろん良いのですが、簿記の知識に自信のない方でも青色申告用の会計ソフトを上手に活用することで、簡単にこれらの書類を作成できます。
また、更に節税を目指し、インターネットを使用したe-Tax(電子申告)を行うこともオススメです。
「青色申告」お役立ち情報 記事
本コンテンツについて
紺野税理士事務所 (山形県鶴岡市)
国税庁より
- 帳簿の記帳のしかた(農業所得者用)
- 令和元年分青色申告決算書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分白色申告者の決算の手引き(農業所得用)
- 令和元年分収支内訳書(農業所得用)の書き方
- 令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用
- 番号法施行規則の改正についてのお知らせ
- はじめてみませんか青色申告(令和3年5月)
- よくわかる消費税軽減税率制度(令和元年7月)
- 各種パンフレットなど
- 本コンテンツで提供される資料における制度や手続き及び要件等は、国税庁の資料や弊社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 本コンテンツ内で提供される資料中の数値、図表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更又は削除する場合があります。
- 本コンテンツは、一般的な内容としてまとめており、個別の事例に応じた内容とはしておりません。
- 本コンテンツの情報を参考にした税務処理による損害、若しくはその情報利用により被ったいかなる損害については、一切その責任は負いません。
- 税務処理については、各事業者の責任に基づき適切に処理を行ってください。
- 本コンテンツで紹介した情報は、個人の農業事業者向けにわかりやすく記載をしておりますが、一定の要件や届け出などが必要となる場合があります。詳細については、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本コンテンツに掲載されている内容の著作権は、原則として弊社に属しています。
- いかなる目的であれ電子的・機械的手段を問わず、著作権法により掲載内容を弊社に無断で複製、引用、転載等を行うことはできません。
- 本コンテンツにリンクを設定する場合は、その旨弊社までご連絡ください。
- なお、リンクを設定するサイトの内容やリンクの方法によっては、リンクをお断りすることがあります。
- 本コンテンツから弊社以外の第三者が運営するサイトへの自動リンクが設定されている場合がありますが、これら第三者サイトの内容の正確性や信頼性等についてなんら保証するものではありません。
- また、これら第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切責任を負いません。
- 本コンテンツに関する紛争を含む一切の事項は、日本法を準拠法とし、山形地方裁判所鶴岡支部をもって第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
この記事は参考になりましたか?
この記事は参考になりましたか?